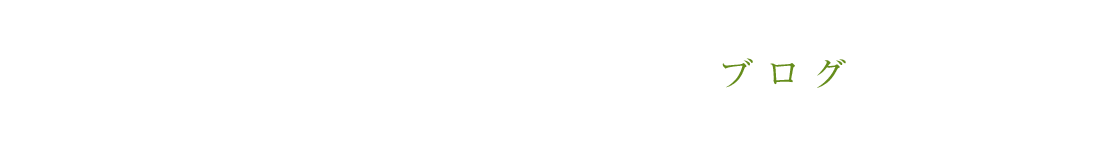登場人物 父・母・子
父が自宅所有 家の価値が2000万円とします。
これでお父さんが亡くなった場合
配偶者居住権のメリット
お母さんが、法定相続分で、お金をより多くもらえることです。
配偶者居住権の財産価値は、お母さんの年齢により平均余命を勘案して決められます。
例えばお母さんが、
65歳なら半分くらい(約1000万)
80歳なら30%くらい(約600万)
90歳なら15%くらい(約300万)
これを無償で相続するので、
お母さんが家を配偶者居住権で相続すると、より多くのお金を相続できるということになります。
配偶者居住権のデメリット
1.認知症対策
配偶者居住権は登記されます。もしこの家を売却する必要が出てきた場合、この配偶
者居住権をお母さんが放棄し、登記を抹消する必要があります。この時、もしお母さ
んが認知症だった場合、配偶者居住権を放棄して、抹消登記をすることができなくな
り、家の売却手続きが進まなくなってしまいます。
2.税務上の問題
お母さんが配偶者居住権を放棄した場合、配偶者居住権分の価値を子がお母さんから
贈与を受けたという考え方になると思います。
まだ事例がないので何とも言えませんが、贈与税が発生する可能性はあります。
いずれにせよ、不動産を売却する可能性がある場合、配偶者居住権には注意が必要かもですね。